窓の外では、柔らかな風が桜の花びらをひとつふたつ乗せて緩やかに流れていた。
そんな春の日に、19才の青年がその生涯を閉じた。
6畳間の部屋の片隅の机の上には、青年の写真が置かれていた。
その前に座っている母親の膝には、「カー」と名付けられた子犬が抱かれていた。
青年は母親と二人、アパートでつつましく暮らしていた。
父親とは、青年が6才の時から会っていない。
青年が物心がつく頃から父親が理由もなく青年に暴力を振るうようになり、母親が青年を守るように家を出たのだった。
青年は小学校の1年生の時からずっと引きこもって暮らしてきた。
父親に虐げられた記憶から、人と関わることに怯えを抱いていたのだった。
それは母親に対しても同じであった。
「おはよう。」の挨拶も交わさず、テレビから流れ出る音だけがその家の空間を震わせていた。
母親は、会話を交わさず心を通わせない子供にいつも淋しさを感じていた。
青年が18才の時に病名を告げられた。
それは、青年から未来を切り取るような宣告だった。
「なんで、この子にだけ辛い思いをさせてしまうの。」
「なんでみんなと同じように、笑顔になったり幸せになることが許されないの。」
母親の心の中をあらゆる感情が湧き出て増殖していったが、青年の前では涙を見せることはなかった。
母親は、出来る限りの医療を子供に受けさせてあげるために懸命に働いた。
夕方や土日にはコンビニでバイトをし、夜は子供の好きな料理を作り続けた。
限られた時間の中、子供と接する時間を削ることは母親にとっては身を切る思いだったが、それは湧き出てくる感情を疲れの中に閉じ込める為でもあった。
「俺も、コンビニで働いてみようかな。」
ある日、青年の声が壁を通して隣の部屋から聞こえた。
母親は、その声にどう反応していいのかわからなかった。
久しぶりに自分に向けられた声、嬉しさと懐かしさの中「うん。」という言葉しか発することができなかった。
しばらくして、青年も母親と同じコンビニでアルバイトをするようになった。
挨拶することですら他人に恐怖を感じる青年を奮い立たせたものは、病気への恐怖ではなく母親への申し訳ない気持であった。
着飾ることもなく働きづめの母、子供の自慢をできない母、そして子供の成長を夢見る事の出来ない母に対しての。
「い、いらっしゃい・・」
視線をレジカウンターを見下ろしたまま発する青年の声は、震えていた。
「あ、ありがとう・・ございました。」消え入るような青年の声。
それは、離れて立つ母親の心に暖かな感情を溢れさせた。
青年は、19才のある日一匹の子犬を家へ連れ帰った。
青年はその子犬に「カー」と名付けかわいがった。
「カー、よしよし。」「カー、無理すんなよ。」「カー、ごめんね。」「カー、ありがと。」
ドア越しに青年の声を聞けることが母親の慰めとなっていた。
そして、青年は亡くなった。
母親は理由のない悔恨と悲しみ、そして淋しさに包み込まれていた。
そんな母親を子犬が慰めていた。
ある日、母親は子犬を洗うために小さな首輪をはずした。
小さな名札のついた首輪だった。
母親は何気なくその名札を見ると、大きな嗚咽が湧き上がってきた。
その名札には青年の小さな文字が書かれていた。
―母さん―
「カー、無理すんなよ。」
「カー、ごめんね。」
「かあさん、ありがと。」
小さな空間に言葉の花びらが降り積もっていった。





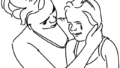
コメント